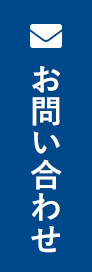さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和7年度(2025年度)の税制改正により、「基礎控除」や「給与所得控除」の金額が引き上げられることになりました。この改正は、令和7年(2025年)分の所得税から適用されます。
「控除が増える」というと、納める税金が少なくなることが期待されますが、注意しておきたいのは「いつから」「どうやって」反映されるのかという点です。

年末調整に向けた準備が重要
今回の改正では、給与から毎月天引きされる「源泉徴収」の金額に関して、令和7年の1月から11月まではこれまでと同じ方法で計算・納付を行います。つまり、改正前の源泉徴収票税額表で源泉徴収をし続けることになります。
そして、令和7年12月の年末調整で、「改正後の新しい控除額に基づいた1年分の本来の税額」と、「改正前の厳正徴収税額表に基づいた毎月天引きしていた税額」との差額を精算する、という流れになります。
控除額の変更内容
具体的には、以下のような変更があります。
基礎控除
合計所得金額に応じて段階的に増減し、従来の48万円から 58~95万円 に拡大されます。所得に応じて5段階で控除額が決まる新たな仕組みです。
以下の段階表を参考にしてください。なお、令和7年・令和8年分の2年間限定の基礎控除額でとなります。
| 合計所得金額(給与収入の目安) | 基礎控除額 |
| ~132万円以下(給与収入約200万円以下) | 95万円(58万円+37万円) |
| 132万円超~336万円以下(200万円超~475万円以下) | 88万円(58万円+30万円) |
| 336万円超~489万円以下(475万円超~665万円以下) | 68万円(58万円+10万円) |
| 489万円超~655万円以下(665万円超~850万円以下) | 63万円(58万円+5万円) |
| 665万円超~2,350万円以下(850万円超~2,545万円以下) | 58万円(58万円+加算なし) |
給与所得控除
最低保証額が10万円引き上げられ、一律65万円 になります。
このように控除額が増えることで、課税対象となる所得が減るため、結果として所得税の負担が軽くなる人が出てきます。
支給日ベースで整理を
企業の給与支給が「毎月15日締め・翌月25日払い」といった形の場合、12月と1月をまたぐ給与については、「支給日ベース」で改正の適用時期を判断するのがポイントです。
たとえば、
〇12月分給与(11月16日~12月15日分/支給日:12月25日)
→ 令和7年分の年末調整にて“改正後”の控除を反映
〇1月分給与(12月16日~1月15日分/支給日:令和8年1月25日)
→ 令和8年の“源泉徴収”から“改正後”の新しい税額表を使用
このように、実際の給与支給日で切り分けて整理すると、改正内容の適用時期が明確になります。
まとめ
今回の令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられ、多くの方にとって所得税の負担が軽くなる可能性があります。
一方で、控除額が「段階的」に設定されていることから、従来よりも所得の把握や区分の確認が重要になります。
控除の一部は年末調整や確定申告で精算されるため、「月々の給与では変化がない」というケースもあります。
とくに、月次の源泉徴収では旧税額表が使われることに注意し、年末に「多く戻ってくる」可能性があることを理解しておくと安心です。
また、企業の給与計算や年末調整を担当する方にとっては、年末に向けての準備が例年以上に重要です。
従業員の合計所得金額を正確に見積もり、適切な控除額を適用することで、税務ミスや従業員からの問い合わせを防ぐことができます。
最後に、この制度は令和7年・8年の2年間の特例的な措置であり、令和9年からは再び一律の基礎控除(58万円)に戻る予定です。年によって仕組みが変わることから、制度の変化を継続的に把握することも求められます。
控除の仕組みは一見複雑に感じられますが、自身の所得や給与明細、年末調整書類などを見直す良い機会でもあります。
この改正をきっかけに、ご自身の「税金とのつきあい方」を見直してみてはいかがでしょうか。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)