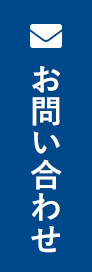さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
生命保険を途中で解約した際に支払われる「解約返戻金」
長年支払ってきた保険料の一部が戻ってくるお金ですが、その全額が非課税というわけではありません。
契約内容や返戻金の金額によっては「所得」として課税され、確定申告が必要になる場合があります。
今回は、個人の生命保険契約における解約返戻金の税務上の取扱いについて、会計事務所の視点から整理して解説します。

解約返戻金は「一時所得」に該当する
契約者(=保険料を負担している人)と受取人が同一の場合、解約返戻金は所得税法上「一時所得」に分類されます。
一時所得とは、営利目的の継続的な取引によらない、一時的・偶発的に得た所得のことです。
課税の対象となる金額は、次の計算式で求められます。
| 一時所得 = 受取金額 - 支払保険料等 - 特別控除(最高50万円) |
そして、この一時所得のうち課税対象となるのはその1/2です。
つまり、利益が50万円以下であれば課税されず、所得税の確定申告も不要です。
ただし、解約返戻金以外にほかの一時所得(懸賞の賞金やふるさと納税の返礼品など)がある場合は、それらを合算して計算しましょう。
確定申告が必要なケース・不要なケース
上記の計算により、利益が50万円を超える場合には課税対象となり、確定申告が必要です。
複数の保険を同時に解約した場合は、すべての解約返戻金を合算して判断します。
また、給与所得者(会社員など)であっても、他の一時所得と合わせて50万円を超える場合や、課税所得が生じる場合には確定申告が必要です。
「会社員だから申告不要」と誤解している方が多いため、この点は特に注意が必要です。
贈与税の対象になるケースも
契約者・保険料負担者・受取人の関係によっては、所得税ではなく贈与税の課税対象になるケースもあります。
たとえば、契約者が夫で受取人が妻の場合、妻が受け取った解約返戻金は「夫からの贈与」とみなされ、贈与税が課されます。
一方、契約者と被保険者が異なり、受取人が第三者の場合は、相続税の対象になることもあります。
契約関係によって課税区分が大きく変わるため、申告漏れや誤った申告に注意が必要です。
| 契約者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税金の種類 |
| 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(一時所得) |
| 本人 | 本人 | 配偶者 | 贈与税 |
| 本人 | 本人 | 相続人(相続が発生している場合) | 相続税 |
補足すると、贈与税においては年間110万円以下であれば、基礎控除内となり贈与税が発生しません。
ほかに贈与があれば、解約返戻金とあわせて金額の確認が必要です。
満期保険金・死亡保険金との違い
生命保険で受け取るお金は、すべてが解約返戻金と同じ扱いではありません。
満期保険金や死亡保険金の場合も、契約者・受取人・被保険者の関係により、所得税・贈与税・相続税のいずれかに分類されます。
たとえば、満期保険金を受け取る場合、契約者と受取人が同じであれば一時所得となりますが、受取人が異なる場合は贈与税の対象です。
死亡保険金は、被保険者の死亡によって支払われるため、原則として相続税の対象になります。
まとめ
解約返戻金に税金がかかるかどうかは、
●契約者・受取人・被保険者の関係
●支払保険料・受取金額の差額
によって判断されます。
利益が50万円以下であれば申告は不要ですが、複数契約を解約した場合や金額が大きい場合は、確定申告が必要になることがあります。
また、契約者と受取人が異なる場合は、贈与税や相続税の対象となることもあります。
契約内容や支払明細書を確認しても判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
税理士法人新日本経営では、確定申告書のご相談から作成まで、一貫してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
参考:No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合|国税庁
確定申告もお任せください◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談を!
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)