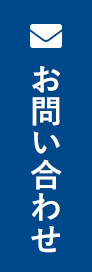さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の額が引き上げられ、非課税となる給与収入の上限が拡大しました。これを受け、青色事業専従者給与の支給額を見直す動きも見られますが、安易な増額は注意が必要です。
今回は、改正の内容とともに、支給額変更時に求められる要件や実務上の留意点について整理します。

所得税の非課税額引き上げ
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額が95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。
これにより、合計所得金額132万円以下の場合には、年間の給与収入が160万円までであれば所得税が発生しなくなりました。
この変更を受けて、これまで青色事業専従者給与を103万円以内に抑えていたケースで、支給額を160万円に見直そうとする動きが一部で見られています。
おすすめコラム>>>令和7年どう変わる?所得税の基礎控除・給与控除の引き上げと特定親族特別控除(仮称)
支給額の変更には、「支給額が労務の対価として相当であるか否か」を判断
しかしながら、こうした変更を行う場合には注意が必要です。
青色事業専従者給与の支給額は、たとえ税制の改正を背景にしていたとしても、単なる非課税枠の拡大に合わせて安易に増額してよいものではありません。
支給額を変更する上で特に重要になってくるのは、「支給額が労務の対価として相当であるか否か」という点です。
労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度、事業の種類や規模、さらには類似業種における給与の状況等など、複数の要素を総合的に勘案して、妥当な金額かどうかを検討する必要があります。
そもそも青色事業専従者給与の特例とは?
青色事業専従者給与の特例とは、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合に、その給与を必要経費として認める仕組みです。
これらの給与は原則として必要経費にできませんが、一定の要件を満たすことにより経費として認められます。
| 青色事業専従者給与を経費にするための一定の要件 |
| ① 給与の支給先が青色事業専従者であること イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること ハ その年を通じて6か月を超える期間(※)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること (※)一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間 |
| ② 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署に提出していること |
| ③ 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること |
| ④ 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること |
これらの要件をすべて満たしていなければ、支払った給与は必要経費として認められません。
おすすめコラム>>>家族への給与を経費にしたい「専従者給与」について
まとめ
なお、令和7年度の改正前には、基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円と設定されており、給与収入が103万円以下であれば所得税がかからないため、青色事業専従者給与の支給額をこの範囲内にとどめる事例が多くありました。
今回の控除額の見直しにより、所得税の非課税枠が広がったとはいえ、支給額の変更には一定の妥当性が求められます。
例えば、青色事業専従者に限らず、アルバイトやパート等を含む全従業員の賃上げとして支給額を引き上げる場合等が挙げられます。
今後、青色事業専従者給与の見直しを行う場合には、改正内容だけに着目するのではなく、実際の業務実態や労務内容とのバランスを見極めたうえで、妥当な金額設定を心がけることが重要です。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶お気軽にご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)